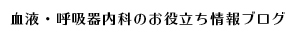鼻出血(鼻血が止まらない):粘膜出血
出血症状としては、紫斑(青あざ)、鼻出血(鼻血)、口腔内出血、消化管出血、過多月経、外傷時出血、脳出血、肺出血など多くの臨床症状があります。
その中でも、粘膜出血の一つである鼻出血(鼻血が止まらない)は、外来でご相談いただく出血症状として、紫斑などとともに最も多い出血症状の一つではないかと思います。
鼻出血の原因としては多くのものが知られていますが、大きく以下の2つに分類されると思います。
1) 耳鼻咽喉科の疾患:
たとえば、鼻ポリープ、鼻腔の腫瘍、鼻腔の炎症などです。換言しますと、鼻出血の患者様を拝見しましたら、耳鼻咽喉科は必ず受診した方が良いです。上記の疾患があるかどうかによって、治療方針は大きく変わります。
2) 全身性出血性素因:
全身性出血性素因の一症状としての鼻出血が見られる場合です。血液内科で扱う疾患になります。
耳鼻咽喉科から、出血性素因がないかどうかということで、ご紹介いただくことも多いです。
全身性出血性素因は、さらに以下のように分類されます。
1. 先天性出血性疾患:
von Willbrand病(フォン・ヴィレブランド病;旧日本語名称はフォン・ビルブランド病;VWD)は、鼻出血などの粘膜出血が見られやすい疾患です。この疾患であるにもかかわらず、診断がされていないいわゆる隠れvon Willbrand病の方も少なくないものと思っています。
2. 後天性出血性疾患:
多数の疾患があります。たとえば血小板数が低下するような疾患です。あるいは、消炎鎮痛剤(アスピリン、インドメタシンなどなど)の連用でも、血小板の機能が低下して出血傾向をきたすことがあります。健康食品(抗動脈硬化作用を有すると書かれている食品など)の一部に、血小板の機能を抑制するものがあります。
さて、鼻出血の患者様を拝見した場合に、
血液内科としてはどのような検査をすれば良いでしょうか。
以前も記事(全身性出血性素因の最初の検査)にさせていただいたように、
以下の検査は必ず行う必要があります。
<鼻出血の検査>スクリーニング
1)血算(血小板数を含む)
2)プロトロンビン時間(PT)
3)活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)
4)フィブリノゲン
5)FDP
6)出血時間(必要に応じて、初めから血小板凝集能を行うこともあり)
:鼻出血が主訴の場合には、やはり血小板凝集能は初めから行なうべきでしょう。von Willebrand病(VWD)では、リストセチン凝集の欠如と言う特徴的な所見が見られます。
PT(PT-INR)やAPTTではスクリーニングされない第XIII因子、α2PIも測定しておいた方が無難です。
また、特に鼻出血の場合には、APTTや出血時間が正常でも、von Willebrand因子(VWF)抗原&活性、第VIII因子も測定する必要があります(軽症のvon Willebrand病ではAPTTや出血時間でスクリーニングされない場合があります)。
von Willebrand因子の低下が確認された場合には、von Willebrand因子マルチマー構造解析、Family studyが必要になります。
von Willebrand病の中でも、最も老いtype Iでは、常染色体優性遺伝します。
Family studyは、発端者の診断にも意味がありますが、家族を守る(大事にいたる前に、von Willebrand病の人を前もって診断して将来の適切な診療につなげる)という意味でも重要です。
なお、注意点があります。
血液型O型の人は、これだけでvon Willebrand因子が低下することがあります(血液型O型の人は、vWF活性が低い)。
ですから、慎重に診断する必要があります。
関連記事のご案内:
凝固検査のカテゴリーへ【推薦】:医療関係者用
播種性血管内凝固症候群(DIC)<図解>のカテゴリーへ【推薦】:医療関係者用
出血性疾患のカテゴリーへ
金沢大学 血液内科・呼吸器内科HPへ
金沢大学 血液内科・呼吸器内科ブログ(血液・呼吸器内科のお役立ち情報)へ
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:30 | 出血性疾患 | コメント(0)
タール便(黒色便)と血便
1.タール便(黒色便)とは
推薦書籍:「臨床に直結する血栓止血学」
黒色便が見られる疾患が知られています。若い方は、タールと言ってもピンとこないかも知れません。道路を舗装する時に使うコールタールが語源です。そのコールタールのように黒い便ということで、タール便と言います。黒色便ということもあります。
参考書籍:「臨床に直結する血栓止血学」(出血性疾患&血栓性疾患について詳述されています)
2. どういう時にタール便が見られるか?
これは、胃や十二指腸から相当出血している時に、みられる特徴的な便です。胃酸と血液が混合することで、黒色便になります。
具体的には、以下のような疾患でタール便が見られます。
1)胃から出血する疾患:胃潰瘍、胃癌、重症の胃炎など。
2)十二指腸から血が出る病気:十二指腸潰瘍、十二指腸乳頭部癌など。
3)食道から血が出る病気:食道静脈瘤、食道癌(いずれも出血を伴う場合)など。
4)大量の鼻出血・口腔内出血を飲み込んだ場合など。
ただし、少量の出血では、タール便にはなりません。たとえば、早期胃癌で、わずかの出血しかない場合にはタール便になることはないでしょう(そういう時には、便潜血検査←クリック を行います)。
タール便がみられましたら、胃や十二指腸からの相当量の出血があることを意味しますので、早々に胃カメラなどの検査が必要です。
一方、直腸癌など、肛門に近い部位からの出血では、タール便にはなりません。この場合は、暗赤色の血便になるでしょう。あるいは、痔からの出血では、鮮紅色の血液が便に付着するでしょう(下記)。
3.タール便と、血便の違い
血便は、文字通り、便に赤い血液が混じります。暗赤色のこともあります。
血便の場合は、大腸癌(直腸癌を含む)や重症の大腸炎などがある場合にみられます。血便は、胃酸の影響のない部位からの相当量の出血で見られる症状です。
痔(特に切れ痔)でも、しばしば便に血が混じります。切れ痔の場合は、便の上に血液がのるという感じになります。便に血液が混入すると言っても、タール便(黒色便)と血便では、意味するところが違うのです。
4. 抗血栓療法とタール便
抗血栓薬というのは、文字通り血栓症の発症を抑えるお薬です。具体的には、抗血小板薬のアスピリンや、抗凝固薬のワーファリンなどです。
抗血栓薬を内服していますと、出血の副作用がみられることがあります。たとえば、紫斑(青あざ)が出やすいかもしれませんし、怪我をした後も止血しにくいかも知れません。
しかし、胃や十二指腸に病気がないのに、抗血栓薬を内服していてタール便がみられることはあまりありません。
ただし、抗血栓薬を内服していますと、小さな潰瘍や癌であっても止血しにくく、タール便になりやすい可能性はあります。この点、抗血栓薬の内服によって、タール便という症状が増幅しやすい(早期診断につながりやすい)可能性があります。
5. 解熱鎮痛薬(NSAID)とタール便
風邪薬には、しばしば解熱鎮痛薬が含まれています。医学的には、非ステロイド系消炎鎮痛薬(NSAID)と言います。
この解熱鎮痛薬には、いろんな種類がありますが(古くは、アスピリンやインドメタシンがあります)、時に、胃粘膜に障害を与えて、胃潰瘍を起こすことがあります。
胃潰瘍を起こしますと、胃の中に出血をきたし、胃酸と混じることで、タール便(黒色便)がみられることがあります。風邪薬をのんでいて、黒い便が出たというのは、風邪薬のなかの解熱鎮痛薬の成分で胃潰瘍を起こした可能性があるのです。風邪薬を処方する際、しばしば胃薬を含めますのは、そのような背景からです。
なお、管理人自身の経験ですが、風邪薬を内服すると必ず毎回黒い便が出るという患者様がいらっしゃいました。検査の結果、先天性出血性疾患の患者様であることが判明しました。
6. 造血剤と黒色便
貧血のお薬に、造血剤があります。造血剤の中身は、鉄(Fe)そのものです。
実は、造血剤(鉄剤)を内服しますと、便は黒色(タールのように見えるかも知れません)になります。しかし、これはもちろんタール便ではありません。
金沢大学 血液内科・呼吸器内科HPへ
出血性疾患のカテゴリーへ
抗凝固療法のカテゴリーへ
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 05:29 | 出血性疾患 | コメント(0) | トラックバック(0)