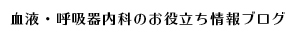ノボセブン(遺伝子組換え活性型第VII因子製剤):究極の止血剤。
遺伝子組換え活性型第VII因子製剤(recombinant factor FVIIa:rFVIIa)(商品名:ノボセブン)をご存知でしょうか。
保険適応は、血友病A&Bにインヒビターが出現した場合の止血管理用、および後天性血血友病のみです。
しかし、ノボセブンは上記の出血以外にも、脳出血(上記疾患とは無関係です。以下同様)、外傷時出血、吐血&下血、血小板数または機能低下時の出血、出産時大出血、心臓手術に伴う出血など多くの出血に対して有効ではないかと期待されています。播種性血管内凝固症候群(DIC)の出血に対して有効という報告(論文抄録)まであります。また、世界的な戦闘地域で、負傷時の止血目的に使用されているという話を耳にしたこともあります。
実際、Pub Medなどで、rFVIIaを検索しますと、本来の血友病インヒビターや後天性血友病の保険適応のある使用の論文よりも、適応外使用の論文の方が多いかも知れません(世界的に適応外使用が数多く行われているのが現状です)。
そのため、適応外使用は慎重に行うべきだという警鐘をならす論文がJAMAに報告(論文抄録)されたほどです。換言しますと、その位、ノボセブンは劇的に効くので愛用する人は多いということではないかと思います。
一度使用経験のある人はあまりに有効であるために、一発でノボセブンのファンになるようです。早く、現在の保険適応の疾患以外にも多くの出血性疾患に使用できるようになって欲しいものです。
なお、現在、ノボセブンの改良型の開発中のようです。より効果の強いアナログ、半減期のより長い改良型が開発中です。将来が大変楽しみです。
(補足) この度、この記事に対して貴重なコメントをいただきました。誤解がないように補足させていただきます。
脳出血に関してましては、rFVIIaは予後や機能障害を改善しなかったというN Engl J Medの報告があります。N Engl J Med. 2008 May 15;358(20):2127-37.
ただし、登録基準設定法や、投与法の工夫、あるいは効果の強いアナログ、半減期のより長い改良型ではどうかなど、まだ可能性はあるのではないかと思っています。
そのあたりを「期待されています」と表現させていただきましたが、誤解を与えてしまう表現だったかも知れません。ここで、補足させていただきます。
また、コメントいただいた方に感謝いたします。
(以下でもリンクしています)
金沢大学 血液内科・呼吸器内科HPへ
血液・呼吸器内科のお役立ち情報へ
出血性疾患のカテゴリーへ
凝固検査のカテゴリーへ
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 10:09 | 出血性疾患 | コメント(2) | トラックバック(0)
血栓性素因の血液検査(アンチトロンピン、プロテインC、抗リン脂質抗体他)
血栓症(thrombosis)は、大きく動脈血栓症と静脈血栓症に分類されます。このうち、特に静脈血栓症に関しては、血栓性素因のチェックが重要になります。
なお、血栓症の分類や抗血栓療法につきましては、以下の記事がご参考になるのではないかと思います。
血栓症の分類と抗血栓療法の分類
抗血小板療法 vs, 抗凝固療法(表)
NETセミナー:血栓症と抗血栓療法のモニタリング
さて、この中でも、血液内科的な血栓性素因にはどのようなものがあるでしょうか?
換言しますと、血栓性素因はないでしょうかというコンサルトを血液内科にいただいた場合に、どのような血液検査をすれば良いでしょうか。
金沢大学 血液内科・呼吸器内科の血栓止血外来にご紹介いただいた場合には、以下の疾患についてのチェックを行っています。
1.先天性凝固阻止因子欠乏症(参考NETセミナー:先天性血栓性素因の診断)
・アンチトロンビン欠乏症
・プロテインC欠乏症
・プロテインS欠乏症
2.線溶異常症
・プラスミノゲン異常症
・高Lp(a)血症:Lp(a)は線溶因子プラスミノゲンと類似構造を有し、拮抗的に作用する。
3.後天性血栓性素因
・抗リン脂質抗体症候群:抗カルジオリピン抗体、ループスアンチコアグラント
・高ホモシステイン血症
<血栓性素因の血液検査として行うべき特殊検査>
アンチトロンビン(AT)、プロテインC(PC)、プロテインS(PS)、Lp(a)、ホモシステイン、プラスミノゲン、抗カルジオリピン抗体、抗カルジオリピン-β2GPI複合体抗体、ループスアンチコアグラント、総PAI、第XII因子
<血栓性素因の血液検査として行うべきルーチン検査>
PT、APTT、フィブリノゲン、FDP(Dダイマー)、TAT(SF、F1+2)、PIC
症例によっては、上記全て必要ではないこともありますので、適宜割愛しています。上記はMAXのオーダーということになります。
なお、上記の検査の結果として血栓性素因の原因が究明される場合に(もちろん究明されないこともあります)、最も多い原因は、少なくとも金沢大学では抗リン脂質抗体症候群(antiphopholipid syndrome:APS)です。抗リン脂質抗体症候群の発症頻度は極めて高いです。
診断のついていない、いわゆる隠れ抗リン脂質抗体症候群の患者様が多数おられるのではないかと推測しています。ひょっとしたら、将来は健康診断項目にリン脂質抗体がはいるのではないかと思っている位です。
関連記事
・ 血液凝固検査入門:インデックスページ ← クリック(全記事、分かり易く図解)
(以下でリンクしています)
金沢大学 血液内科・呼吸器内科HPへ
血液・呼吸器内科のお役立ち情報へ
血栓性疾患のカテゴリーへ
抗凝固療法のカテゴリへ
投稿者:血液内科・呼吸器内科at 04:32 | 凝固検査 | コメント(0) | トラックバック(0)